杉野泰之
営業経理統括部 部長

長く雑誌の仕事に関わっていたため、目に入るもの、耳に入った話を取材対象として魅力的か、そうでないかで判断してしまう悪い癖がある。品がないなぁ…と自覚してはいるのだけれど、長年の習慣はなかなか抜けない。
たとえば、それが人だったとしたら、単に二枚目だとかスタイルがいいという単純なものではなくて、オーラのような不思議な存在感であったり、滲み出すなんともいえない味わいだったりする。
今回登場していただいた杉野さんは、まさにそんな方。かなり前からイベントや展示会などでお見かけしていたものの、話を交わしたことはない。でも、その颯爽としたスマートな雰囲気が妙に気になっていた。
浅草生まれ、浅草育ち。絆を大切にする人情家
杉野さんは、1961年、東京都台東区浅草の生まれ。どことなくさっぱりとした雰囲気はそんな背景のなせるわざなのかもしれない。
「浅草ってサラリーマン家庭が少なかったんですよ。だから休日に親がどこかに連れて行ってくれる…っていうのはなくて、子ども同士で遊ぶことがほとんどでした。自然がない街ですけど、隅田川を渡った先の墨田区に、ひょうたん池っていうのがありまして、自作の竿でクチボソとかフナとか釣ってました。あとは神社で缶蹴りくらいかなぁ。別に塾とかもなかったですしね。みんな受験とは無縁で。ひとりだけ早稲田中学を受けるってヤツがいて、“ワセダってどんな字書くんだ?”って話題になったくらいです」と明るく笑う。
ほのぼのとした昭和の風景は、まさに「三丁目の夕日」の世界だった。
粋を身上とする街でのびのびと育った少年時代。浅草の風土は彼の人となりに何をもたらしたのだろうか。
「宵越しの金は持たねぇ…っていうところはあるかな。きっちりと物事を考える山の手の人間と比べると、僕はコテコテの下町で、“まぁいいじゃん!”って考えちゃうほうなんです。今は、IT全盛で、顔と顔を突き合わせたコミュニケーションが少なくなってるじゃないですか。熱く語り合うとかね。でも(浅草は)人間関係を大切にする。幼馴染みとか町内のおつきあい、絆を大事にするんですね。だからかもしれませんが、ボクは面接でも、きっちり勉強して成績がいい優等生よりは、いろいろな経験を積んできて人の機微がわかる人を採ってきた気がしますね。皆さん、浅草って聞くと“かっこいいね!”とか“粋だね”とか言うんですけど、地元の人間は意外とそういう自覚がないんですよ。多少口が悪いかな…っていうくらい(笑)」
そんな杉野さんだから、多くの部下に慕われてきた。
「昔、私が採用したスタッフ達のことを“杉野組”なんて呼ばれていた時代もあったんです。私が勤続15年を迎えたときのことなんですが、彼らが“たまにはみんなで温泉にでも行きましょう!”って言うんですね。直営店が一斉に休める日はそんなになかったんですが、20人ちょっと集まって。何も知らずに宿に行ってみたら、“勤続15年おめでとうございます!”って。ウルっときましたね。その時にもらった寄せ書きは今でもくじけそうになると眺めていますよ」

新規店を一から立ち上げてみたい…という想い
「中学校から高校まで剣道部。高校生の頃、例の“Made in USAカタログ”が出たんですが、私はどっちかといえば浅草の仲見世で売ってるような黒と白の縞々のシャツとか、エナメルの靴が好きなタイプでしたからねぇ(笑)。大学に入ってようやくハイカラな友達ができて、246号線(青山通り)にできたブルックスブラザーズに行くようになったんです。ビーチサンダルで行っちゃって場違いだったなぁ。波乗りを始めたのもその頃。それで、海岸でバーベキューやったりして、ツーバーナーを初めて見たんです」
やがて杉野さんは、銀座の老舗文具店で社会人としてのスタートを切る。デザイン用品売り場で、販売のプロとしてさまざまな知識と経験を積み重ねていった。
「11年ほど勤務して、結婚もしてたんですが、求人誌を眺めていたら、コールマンが茅場町の本社の一階に直営店を出すことになると書いてあって“店長候補募集”と出てたんです。見慣れたロゴが目についたんですよね。一からお店を立ち上げさせてもらえることにやりがいを感じて応募しました」
入社は1994年の3月8日。開店の4月17日までひと月しかない。その日から勝負が始まった。
「入ったその日から、レジ業者とか包装紙を手配して…(笑)。でも、やっぱり外資系は違うなぁ…と思ったのは、いきなりホットパンツのきれいな女性社員が横を通っていったんですよ。前の会社は銀座の老舗だったので堅い会社でね。日焼けしても怒られたくらい。コールマンは制服もないし、自由な社風でした。上司の意向もあったんでしょうが、なんでも任せてやらせてくれましたよね。とても勉強になりました。コールマンに入っていちばんよかったのは、心からキャンプを楽しみたいと思って来てくださるお客様がたくさんいたことですね。当時、アメリカから取り寄せた古い商品を並べてミュージアムと呼んでいたんですけど、その写真を撮るためにわざわざ愛知から来てくださったりとか…。人生の楽しみのお手伝いをしているという手応えがうれしかったです」

アウトレットという新たな挑戦
1996年、杉野さんは松戸にプロダクトセンターを立ち上げる。それは、返品対応や修理を行ない、商品に関するさまざまな情報を吸い上げる拠点だった。杉野さんは箱崎のショップとこのセンターの統括を兼任し、さらに新たな試みに取り掛かる。
「ちょっとした傷だけの返品も多かったので、それを調整したり修理して売ってみようと。撮影にちょっと使用しただけ…とかもね。1997年のことです。プレハブの建物で、床とか壁はスタッフで作りましたよ。クッションタイルなんて、2トントラックで買いに行ってみんなで貼ったんです。楽しかったなぁ…。土日の賑わいが終わると月曜には商品がすっからかんなんですよね。あまりの人気に、レジがお札で閉まらなくなっちゃって(笑)。当時の上司が“杉野、だから商いは飽きないんだよ”っていった言葉が今でも忘れられないですね」
ショップの開店、松戸のプロダクトセンター、同アウトレットを開設した杉野さんは、大阪のりんくうタウンの立ち上げに着手。その後のアウトレット店の礎を創った。こうした、エンドユーザーに向き合う日々が杉野さんを支えていったのである。
「私は小売りの時代が長かったので、基本的にはエンドユーザーと接することが多かったんですが、すごく幸せだったと思いますね。今でもキャンプイベントに行くと夜に差し入れしてくれたりとかね。ファミリーセールでわざわざ私を捜し出してくれて“元気ですか?”なんて」
国境を超えた仕事の難しさと壁
2013年、コールマン全社におけるグローバルな経理処理など基幹システムの統合の際に、杉野さんは営業の代表としてアメリカへ渡り交渉に当たった。それは経験したことのない困難の連続だった。
「たいへんでしたよ。国が違うと商売の仕組みとか規模、流通が全然違いますからね。お店や修理、サービスセンターとかは、経験をもとに対応できてたんですけどね。今回は過去の経験では対応しきれませんでした。国民性の違いもありますしね」
韓国での直営店開設でもやはり同じような苦労があったと笑う。
「羽田からひとりで出かけたんですけどね。言葉も分からないまま、オフィスに行ってみて10人くらいのスタッフ候補に“キャンプやったことある人は?”って聞いてみたら誰も手を挙げない(笑)。で、開店までの10日のうち2日使って公園で道具のメンテナンスとかダッチオーブンの使い方とか教えてね。店舗に行ってみたらすごくカッコイイんだけど、カウンターが高過ぎて。“これじゃテントを乗せられないでしょ”って切らせたり。いちばんビックリしたのは、ランチを終えて帰ってきたら店の中が何か匂いがするんです。見たら、バイト君たちが店舗の販売スペースで食事してるんですよ。ボクらは普通バックヤードとか見えない所で食べますけど、向こうではロッテ百貨店などでもそんな光景が普通のようで(笑)。“ここはコールマンというアメリカのブランドの一号店だからそれはやめてね…”って説明しました。また、開店前夜、棚の商品が並び終えてないのに挨拶の練習を始めちゃったりね。いやいや、店を開けられる状態にするのが先でしょ?って(笑)」
とはいえ、その後の商品作りや販売へのヒントも多かったという。
「韓国ってクリスマスとか寒い時期のキャンプが盛んだったりして、スペックに関しては結構シビアでしたね。細かいことにとてもうるさい。火力調整をもっと細かくできないか?とかね。思いもよらないリクエストがあったりもするんですよ。“なんで寝袋に枕がついてないの?”とかね。別売りなんです…って言うと、寝る時に枕は付きもんだろう!って顔をしたりする(笑)。でも、街がエネルギーに満ちていて人情味があって楽しかったですよ」

いつも見ているのはエンドユーザーの顔なんです…
こうして現在は販売の現場から離れている杉野さんだが、ユーザーへの熱い想いは変わらない。
「今はオフィスにいる時間が長いので少し寂しいですけどね。でもやっぱり意識するのはエンドユーザーの存在です。たとえば、ある商品がたまたまバカ売れで品切れしちゃって受注をいただいたような時に、少しでも早く、少しでも公平にお客様へお届けしたいと思います。そこにあるのは、使ってくださるエンドユーザーへの気持ちなんです。楽しい時間を過ごしていただけるように、お手伝いしたい…。
何年か前、どこかの自動車会社が“モノより思い出”なんて広告コピーを使ってましたけど、ヤラれたなぁ…って思いましたもん。そういうことだと思うんですよ。うちの子は24歳と21歳なんですけど、やっぱり覚えてるんです。子どもの頃キャンプに行った思い出を。テントで初めて寝た時のこととか、バーベキューの味とかね。ひとりでも多くの方に使ってもらって、そんなふうに幸せを感じてほしいと思いますね。何度も言いますが、ボクに見えてるのはいつでもお客さんの顔なんです」
杉野さんは、コールマン製品もユーザーの傍らで素晴らしいひとときを共有してほしいと願っている。
「3,4年前にCOCが野麦峠のほうでキャンプイベントをやったことがあるんです。その頃、胃潰瘍になっていて…。イベントではお酒も呑みますしね。このまま行ったらヤバいなぁ…なんて思いながら向かったんですけど、会場で設営に取り掛かったら、大きなトノサマバッタが次々飛びかかってくるんですよ。普通なら逃げていくでしょ?でも、その時は“お前ら、ここは俺たちのテリトリーなんだぞ!ジャマだ!”って挑まれてるような気がして、その自然のパワーに感動しちゃったんです。嬉しかったんです。そうしたら胃潰瘍が治っちゃった(笑)。自然の素晴らしさに感動するそんなひとときって、誰でもあると思うんですよね。その傍らにランタンひとつでもいいから、私達の製品があったらうれしいですね」
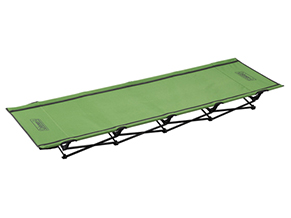
インタビューの間に杉野さんは何度もコールマンで働く喜びを口にした。そこにはブランドへの誇りもにじむ。
「社員がみんな、部署や年齢、立場に関係なくコールマンというブランドを愛していて、誇りを持ってそれぞれの担当業務を担っています。エンドユーザーの方々も、コールマンブランドの製品を所有し、使用する誇りと信頼感・優越感を抱いて頂いていると感じます。そうした“人”の熱い思いの集まりが、コールマンというブランドをさらに輝かせてくれるんですね。“人”が誇りをもって開発し、流通し、店頭で販売する…それがユーザーに伝わって、さらに満足度がアップする。これぞまさしく“コールマンらしさ”だと考えます。私は、こうしたコールマンらしさ、魂を持った上司や同僚、部下、お客様に囲まれ、力を貰ってきました。これからも、この素晴らしい人達と一緒にさらによいブランドにしていきます!」
こんな言葉をさらりと口にして、杉野さんは部屋を後にした。
将来の夢は?と問いかけた時のことだ。彼はにやっとして少し小声になった。「単に呑兵衛なんですけどね…リタイヤしたら居酒屋をやりたいなって思ってたりして」。
居酒屋とは接客業の究極なり…どこかの評論家がそんなことを言っていたけれど、やはり客と触れ合う時間が好きで好きでたまらないのだろう。
杉野さんにとって、いつまでも商いは飽きないのである。

取材と文
三浦修
みうらしゅう
コールマンアドバイザー。日本大学農獣医学部卒。つり人社に入社後、月刊 Basser編集長、月刊つり人編集長を経て、2008年に広告制作、出版編集、企画、スタイリングなどを手がける株式会社三浦事務所設立。自称「日本一ぐうたらなキャンプ愛好家」。
1960年生まれ。千葉県市川市在住





















