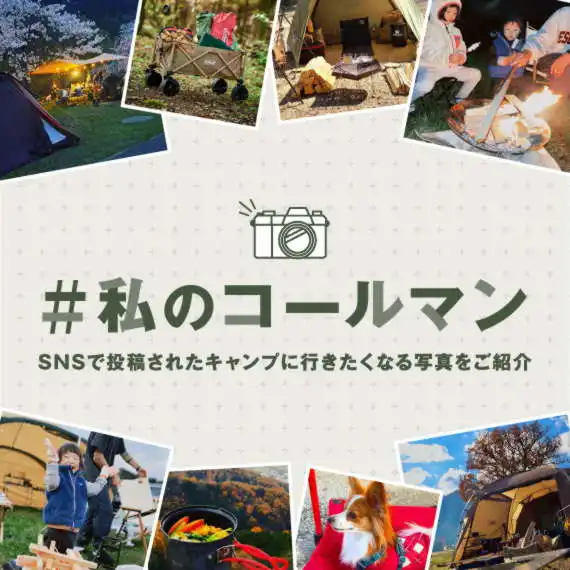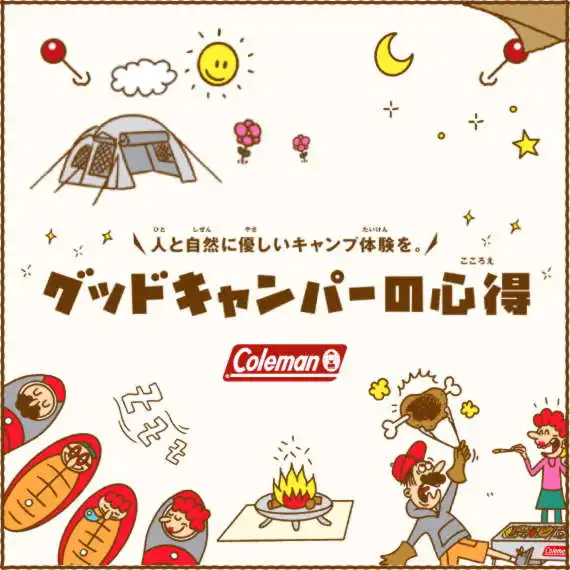藤田祐司
オペレーションズマネジメント本部 アフターサービスグループ プロダクトセンター 係長

100年前のランタンも現役で活躍するコールマンのモノ創り…。しかし、野外の遊び道具である以上、メンテナンスが必要になることもある。ランタンが点かなくなったり、ツーバーナーの炎が不安定になったり…。そんな時、頼りになるのがアフターサービスだが、拠点となっているのが、流山のプロダクトセンターだ。今回訪ねたのは、その修理の陣頭指揮をとる藤田祐司さん。笑い顔がクールな46歳だ。
プロレスラーを目指した中学時代
「生まれたのは東京です。家は新宿の中央公園の近くでしたが、その頃は田舎っぽい雰囲気でした。駄菓子屋でお菓子を買ったり、熊野神社のお祭で神輿が出たり…。歳の離れた兄がリトルリーグをやってて、いつもそれに付き合わされたんですが、こっちは小さいからやることがなくて…。だから、野球は嫌いだったんです」
幼稚園の頃、千葉県の松戸へ転居。生活環境が一変する。
「喘息持ちだったんですけどね、松戸に引っ越したら治っちゃって“空気がきれいなんだね”なんて言われました。今考えれば、光化学スモッグだったのだろうと思います。松戸に来たら兄貴がソフトボールを始め、ここでもイヤイヤ一緒に入れられました。でも、面白くなかった(笑)。普段は、ザリガニ釣りとかやってましたね。このあたりはクワガタも採れたんです」
その頃、彼の心をとらえたのは意外なもの…格闘技だった。
「一番好きだったのはプロレスでした。アントニオ猪木の人気が下火になって、長州力の人気が高まってきた時代です。なのに、私は新日本プロレスではなくて、ジャイアント馬場の全日本プロレスのファン。テリーファンクが好きでした。少年漫画…週刊ジャンプの全盛期ですから、キン肉マンとか北斗の拳なんかの影響もあったんでしょうね。キャプテン翼も流行ってまして、小学校5年生の頃にサッカークラブに入ってみました。でも、大して面白くなかったです(笑)。挫折ばかりなんです」
プロレスへの想いは募るばかり。ついには人生を賭けようとさえ思い始めた。
「中学校では、プロレス熱が高まってしまって、プロレスラーになるにはどうしたらいいだろうと真剣に考えたんです。でも学校にはレスリング部がない。で、柔道部に入りました。でも、プロレスごっこばかり(笑)。それだけで腹筋が割れるくらい熱中しました。そのうち、どうもこれは違うな…と思うようになりました。身体が細くて、このままいってもプロレスラーにはなれないぞと。で、なんとなく柔道部をサボり始めまして、また挫折です」
高校でも紆余曲折が待っていた。
「バスケット部に入ったんです。単に身体が大きくて…という理由で誘われたんですけど、練習がキツくて、夏には辞めてましたね。ずっと走ってるんですもん(笑)。こりゃダメだな…と」
しかし、アルバイトだけは高校時代を通じて続けていたという。
「最初は本屋のレジ打ち。でも、時給が450円とか、信じられないくらい安くて、こりゃ儲からないな…と。いくら働いてもお小遣いにならないのでファミレスに移りました。
その頃、ローリングストーンズがやってきて、公演スタッフがお揃いのポカリスエットのジャンパーを着てたんですね。それが欲しくてバイトで雇ってもらったんです。念願かなって着ることはできたんですが、公演が終わったら回収されちゃって、持ち帰れなかった(笑)。ポール・マッカートニーの時もバイトしたんです。客席のほうを向いて警備するんですけど、“前を(ステージを)見るな!”って怒られるんですよ。でも、ついつい見たくなっちゃいますよね」
とにかく、藤田さんとの時間は笑いが絶えない。自分が披露した話で、自ら笑いをかみ殺す…その姿がまた笑いを誘う。さて、高校を卒業した彼が選んだ道は、コンピュータの世界だった。中学生時代にファミコンの楽しさを知ったのだという。
「高校では遊び足りなくて、とりあえずコンピュータの専門学校へ行くことにしました。中学校の頃にファミコンが出て、すごい行列に並んでドラクエⅡを買いました。画面を見なくても操作できるくらいまでやってました。専門学校では、プログラミングやフローチャートをやっていましたが、あんまり勉強しなかったなぁ…。遊ぶお金を稼ぐため、大久保の喫茶店でバイトしていました。客商売は好きでしたね。でも、一生の仕事にしようとは思わなかったですね。売り上げ管理とかまで任されるようになったんですけど、儲かる商売じゃないなぁ…って思っちゃったんです」
コールマンとの縁をつないだオーストラリア留学
社会人としてのスタートは自動車メーカーだった。
「バブルがはじけた直後だったんで、まだまだ募集が多かったんですね。それで、Hondaのディーラーに勤めることにしました。F-1が好きだったのが理由のひとつ。本田宗一郎さんも好きで、この人を助けられるならいいなぁ…と(笑)」
3年ほど勤務した後、今度は海外へ目を向ける。
「母が亡くなったタイミングもあって、海外に行ってみたいと思うようになったんです。外国人がどんな考え方をするのか興味が湧きまして…。ビザの関係で、アメリカでは長期滞在ができないので、ワーキングホリデーが使えるオーストラリアを選びました。シドニーに向かったんですが、面白かったですねぇ」
渡航まで英語の勉強はまったくしていなかったという藤田さん。そこでも彼らしいエピソードが花開く。
「英語の準備はまったくしていなかったですね。ちょっとナメてました(笑)。洋楽を聞いていて、しょっちゅう歌詞カードを見ていたので、分かったような気になっていました。でも、行ってみたらそんなに甘くなかった(笑)。“Let it be”なんて、日本では“為すがままに”と訳されてるじゃないですか。それを完全に信じてましたからね」
そこで現地の英会話学校に通い始めたのだが……
「一ヵ月くらい通いましたけど、そこは日本人ばかりで英語を話さないので役に立ちませんでした。だって、先生に“日本語でしゃべるな!”って言われると、無言になって静かになっちゃう。みんな英語が分かりませんからね(笑)。これではマズいなぁと…」
しかし、ホームステイをしていたこともあって、少しずつ英語に慣れていったという。
「そのうち中国人とか韓国人とルームシェアを始めたんですよ。とってもフレンドリーな連中なんですけど、そのへんに置いておいた物がどんどん無くなるんですよ(笑)。コーヒーとかドリンクとか…。みんな持って行かれる。貴重な体験でしたね。そのうち、アイリッシュパブみたいなところに通うようになり、酔っぱらって適当な英語を話していたら、お前面白いな…ということで、現地の友達ができました」
BBQを楽しむようになったのもこの頃だったという。
「日本ではほとんどやらなかったんですが、オーストラリアでは公園に設置されてて、ボタンを押して順番待ちするんです。アウトドアという意識はあまりなくて、普通の生活の一部のような感覚で楽しんでました」
やがて帰国した藤田さんだが、現地での生活が楽しくてまだまだ不完全燃焼だったという。再渡航の資金を貯めようと、仕事先を捜して出会ったのがコールマンだった。松戸のプロダクトセンターが修理要員を募集していたのである。
「友人が使っていた蛍光灯ランタンを見たことがあったくらいで、コールマンと言ってもあまり強い想いはありませんでした。ただ、修理って面白そうだなと思ったんです」

修理のスペシャリストとして…
こうして藤田さんは1999年にアルバイトとして採用された。すでに28歳になっていた。
「まったく畑違いですが、自動車の仕事をしていて機械はイジっていた経験がありましたから、違和感はありませんでした。コールマン製品は基本的に構造がシンプルなので、すぐに慣れましたね。職場は、みんな若くて、(バイト仲間は)仕事ばっかりで一緒に遊ぶということはあんまりなかったんです。私はすで28歳で社会経験もあったので、ご飯を食べに誘ったり、飲みに連れ出したり…そういうのがセンターの習慣みたいになっていた時期がありました」
修理のスペシャリストとして着実に経験を積んでいった藤田さんは2002年に正社員となる。
「たぶん、ここだろうなぁ…と目星をつけて修理を進めていくんですが、それが外れると悔しいですよね。逆に一発で当たった時は嬉しいし。でも、たまに無限地獄に入る時があるんですよ。ここも違う、ここもダメだ…って、次々直していくんですが、症状が治らず、結局全部交換…なんてこともあるんですよ」
やがて、現在の流山のプロダクトセンターが稼働する。
「ここに来て、最初は再生チームにいたんです。それからマーケティングのプロモーションとかPRとかで、イベントや取材の備品貸し出しに携わっていて、パーツの発注管理も手掛けました。そして、今年の1月から、修理に戻ってきたんです。修理全体を管理しながら燃焼器を手掛けているんです。15年ぶりくらいで工具に触ったのでドキドキしましたよ」
コールマン ジャパンのアフターサービスはその間に大きな進化を遂げていた。
「私が入った頃よりもずいぶん効率が上がっています。たとえば、電動工具が導入されたり、燃焼器の修理の際、圧縮エアを使ってある程度ポンピングの代わりをするようになって手間が減りました。見積もりの製作もパソコンによってかなり早くなっています」
修理の生き字引のような藤田さんでも手を焼くことがあるのだろうか。
「ツーバーナーで苦労したことがありましたね。時々、炎が消えなくなったと送られてくるのがあるんです。でも、そういう修理って、このあたりが怪しいっていう部分に手を入れた後、全部組み上げないと(消火できるようになったかどうか)テストできないわけです。…で、やっぱり消えない。もう1度バラして修理してみて…やっぱり消えない(笑)。それを何度も繰り返しました」
修理をする上で心掛けていることは?と尋ねると、そこまで快活に受け答えしていた藤田さんがしばし考え込んだ。言葉を選んでいるようにも、過去の経験を整理しているようにも見える。
「お預かりしている物ですから、できる限り丁寧に扱う。それが一番ですね。お客様がどの部分を大切に想っていらっしゃるか分からないわけです。たとえば、塗装が小さなブリスターみたいに浮いちゃってることがあるんですが、触るとはがれてしまいます。でも、そういうことを気にする方もいるし、どこに思い出が遺されているかも分かりません。だから、きれいに掃除してしまうのをためらうこともあります。機能さえ戻ればいい…というのではないんです」
送られてきた修理品に込められた想いや、重ねてきた時間にも気配りする…そんな言葉を聞いて、彼の仕事の奥深さや難しさに触れた気がした。
コールマンの魅力を尋ねると、またあの笑顔が戻ってきた。
「アメリカっぽい大らかなモノ創りがいいんじゃないでしょうか。遊びの道具なので完璧すぎると息が詰まるじゃないですか。クルマのJEEPなんかもそんな魅力がありますよね。そして、ブランドとしては、いつまでもキャンプが好きな方々に必要とされる存在であり続けてほしいと思います。それは、少しずつ姿を変えていってもいいと思うんですよ。たとえば、ホワイトガソリンの商品にLEDが加わってきて、将来はLEDが主力になるかもしれない。それでも、(それが)キャンプ好きな方々に必要とされるものであればいいと思うんです」
締めくくりに彼が口にした言葉は、修理部門の統括者としての誇りに満ちていた。
「ユーザーの方には、コールマン製品をもっとイジってほしいですね。僕もスクーターを自分でいろいろイジってますけど、コールマンはそんなに複雑ではありません。イジらないと構造は分からないからどんどん触ってほしい。そして、うまくいかずにどうしようもなくなったら、任せてください」
自分で道具を修理する…それもコールマン製品の楽しさなんですよ…彼の目はそう訴えていたような気がする。
インタビューを終え、隣接するコールマンショップ流山店に寄ると、熱心にメンテナンスパーツを選ぶファンがいた。傍らには丁寧に応対するスタッフ。それは藤田さんの想いそのものの光景だった。




取材と文
三浦修
みうらしゅう
コールマンアドバイザー。日本大学農獣医学部卒。つり人社に入社後、月刊 Basser編集長、月刊つり人編集長を経て、2008年に広告制作、出版編集、企画、スタイリングなどを手がける株式会社三浦事務所設立。自称「日本一ぐうたらなキャンプ愛好家」。
1960年生まれ。千葉県市川市在住